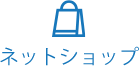<「膠(にかわ)」の語源>
「膠(にかわ」」の語源は明らかになっていません。しかし、ウラル語系の梓弓(あずさゆみ)を作る時の接着剤を意味する言葉から派生したもの、という記述が残されています。
コウ(またはキャウ)という中国語の「膠」が日本に入ってくる前に、「膠」を意味する「にべ」という言葉が日本には存在していました。
その証拠に、「徒然草」には「鯉の煮物を食べると髭ににべがついて」という記述があります。また、和膠生産者は原料の皮を「にべ」と呼び、弓師は膠(にかわ)を「にべ」と呼んでいます。さらに、皮革業界では脱毛した牛の皮を「にべ」と称しています。
<「和膠(にかわ)」の製造工程と最適な乾燥時期>
和膠は60℃前後で8時間抽出し、温度を90℃以上に上げて濃縮し、濃度12%の膠液を回収します。さらに、この取り出した濃縮液を冷却し、凝固させます。乾燥の最適な温度は屋内温度で0℃以上、屋外温度で20℃以下です。膠を凍結させるとコラーゲンの構造が崩壊し接着力が低下するため、0℃以上での乾燥が必要と考えられています。屋外温度とのバランスを考えると、10月後半から4月中旬が乾燥に最適な季節です。
近代日本での生産地が近畿圏であることは、この乾燥条件に適していたことも要因の1つと考えられています。
<墨の歴史について>
墨は、炭素末(煤=すす)と膠(にかわ)、さらに少量の香料を練り合わせたものです。墨の起源は紀元前1500年ころの中国、殷の時代と言われています。漢の時代に蔡倫(さいりん)が紙を発明したことが、墨の需要が急激に伸びた発端です。さらに日本書記には、飛鳥時代の頃に渡来僧が日本に墨を持ち帰った、と記述されています。
墨を作る省庁があり、作り手が公務員であった事も興味深い事実です。正倉院には、最古の墨が保存されているという話もあります。奈良時代になると仏教が盛んになり、写経が行われるに従い、墨の需要も増えたようです。奈良には寺院が多く、必然的に墨の製造業者が発展したようですね。
煤には、松煙と油煙があります。それぞれ書画の味わいに違いがあり、趣を感じます。豊臣秀吉の時代の日明貿易で、広東膠や油煙の原料である菜種油が輸入されてきたことが、煤の拡大に大きな影響を与えたといえます。
煤に含まれる香料は、膠(にかわ)を炊く臭い消しにも使われていた可能性があります。獣臭があると殺生を禁じる仏教の教えに背くことにもなります。この香りが精神を落ち着ける作用もあり、墨を磨ることで精神統一が出来るのかもしれませんね。
液体墨は習字学習に伴い、墨を磨る時間の短縮を要請されたことから開発が進んだようです。膠の代わりに合成樹脂が使用されるようになり、分散性や速乾性の液体墨が普及しました。その結果、現代では固形墨を見かける機会が少なくなったようです。これも時代の流れですが、固形墨の紙での滲み、青味がかった墨独特の色彩は膠の作用と相まって芸術性の高いものであることは変わりがないと思います。固形墨の製作技術の消失も時間の問題で、無くなる前に何とかしておきたいものです。